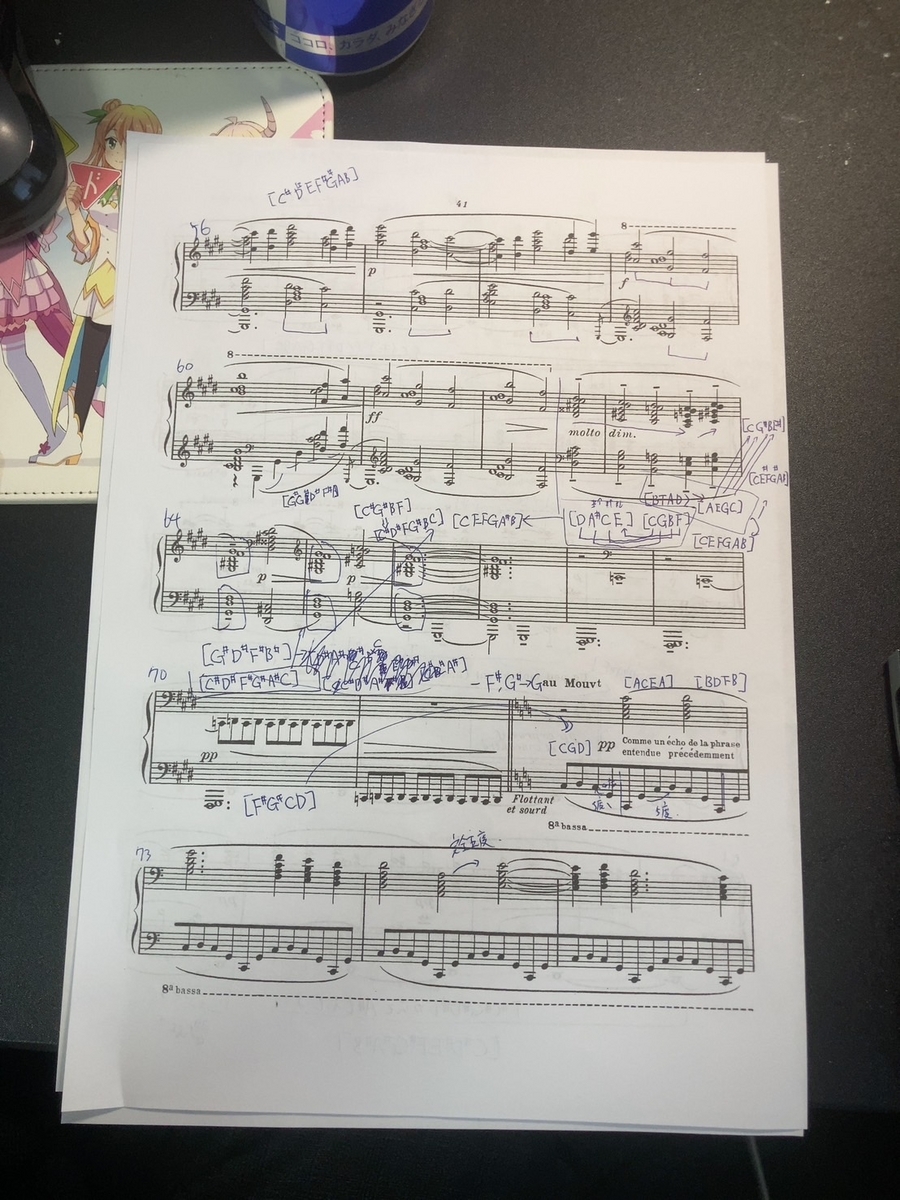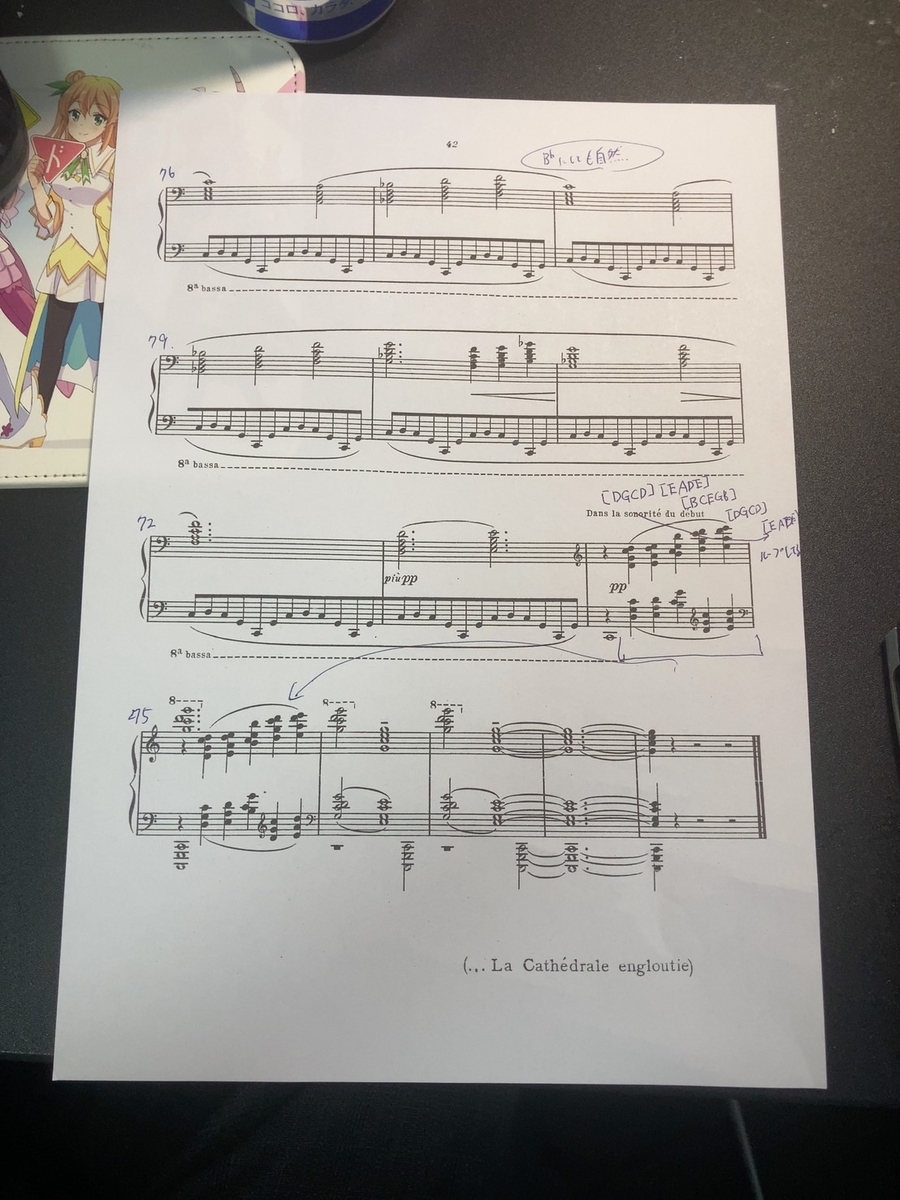いつも私といえばアンチ吹奏楽発言をしている「うるさいおぢさん」の一人なのだが、そもそも私自身は吹奏楽部出身だったりする。初めてそれらしきものに触れたのは小学校のクラブ活動で、はじめの楽器はTubaだった。しかしそれまでリコーダーが得意だった自分には、同じ指使いで様々な倍音を得ることで演奏をする金管楽器がどうにも馴染めなかった。
中学校に入ると「ブラスバンド部」に入部した。当時は、ブラスバンドと吹奏楽、すなわちウインドオーケストラの違いが明確に認識されておらず、ブラバンは吹奏楽と同義語だったわけだ。もともと木管志望でFluteを吹いてみたかったが、吹奏楽あるあるで人数が足りていた事もあって、打楽器パートにスカウトされ打楽器を担当することになった。そのときパートにいた先輩が優秀だったのと、ちょうどその中学では新入部員が多くなり、講師の先生を立てることになったのも幸いして、自分は現代音楽と吹奏楽に強く惹かれていくことになった。ちなみにいまは活躍されている中原朋也先生がお若いときに指導されに来てくれていた。まあ当時の話は黒歴史でしょうから黙っておきます(笑)
すっかり打楽器で気を良くしたのでそのまま音大へ進むことを考え始めたのもこの頃だった。作曲は趣味で小学校3年から始めていたが、このときは打楽器で進むことしか頭になかった。
高校に入ると「吹奏楽部」を志望し、当然打楽器経験者ということで優遇され、そのまま打楽器パートへ。良い先輩と仲間にも恵まれ好き放題できたのも、音楽好きへ拍車をかけた。この頃になると自身の作品も書いて演奏をするということもやっていたし、打楽器を本格的に学ぶべく佐野恭一先生に弟子入したのもこの頃であった。今考えると、部活動でやっている曲を佐野先生のレッスンに持っていっても、全く教えてくれないどころか、そういうものに集中するくらいなら基礎練をするように言われた。当時はその意味がわからなかったが、先生は吹奏楽における打楽器の在り方に疑問を持っておられたように感じる。
そして念願かなって桐朋学園大学音楽学部演奏学科打楽器専攻に入学したのだが、入学して早々に打楽器への熱が失われていってしまった。一つには作曲行為への情熱が高まったこと。もう一つは自分がさして演奏がうまくないことを知ったからというのが大きい。最も決定的だったのは、将来食っていくことを考えたときに、音大という機関がその役割を果たしきれていないことに危機感を感じたというのもある。なんだかんだあって、作曲方面に軸足を移し、校外での活動に力を入れるようになって、気がつけば作曲家、事業家として身を立てることになっていった。
とはいえ、まだ吹奏楽との因縁は続いていて、仕事で指導に回ることが多くなってきた。打楽器パート以外に指揮も振れ、楽曲解釈もできるということで結構たくさんの学校にかかわらせていただいた。その一つに母校の高校があったが、そこでどっぷり吹奏楽の世界にひたり、多分世の中の吹奏楽人口の多くが経験するような、およそ音楽の真の姿とはかけ離れたガラパゴス経験を深めてしまったのだ。
しかし時はたち、Popsのアレンジャーとしても活動をする頃から、部活動の指導におけるギャラのやすさも災いし、学校と多くトラブルを抱えるようになってこの世界に疑問を覚え始めた。
まず第一に指導者にプロが少ない。せいぜい学生のバイトと、専門外上がりの趣味人が指揮をしている環境で、正しい音楽教育がなされておらず、教員で作られる吹奏楽連盟という組織自体の問題や腐敗、一部の学校への利益誘導に辟易させられた。そしてなによりこの頃から、ブレーン社、カフア社、フォスターミュージック社など一部の大手出版社が、レンタルという方法と、一部の作曲家を神格化してブランディングを行うようになって、内容ではなくビジネスモデルとして吹奏楽の世界を自分たちの利益源として搾取し始めたことに苛立ちを隠せなくなってきたのだ。
かくて、吹奏楽で育った青年はこの世界のアンチとなり、もっと本格的な音楽を吹奏楽で演奏できるようにしないと、この世界は閉じきって潰えてしまうという焦りを感じ、「うるさいおぢさん」となって行ったのであった。
と、自分と吹奏楽の関係をまとめて無駄な自分語りをしてみたが、上記に指摘した通り、今の吹奏楽はただの商業音楽が芸術音楽のフリをして歩く、一種のアパレル業界と似た構造になっていると思っている。そしてそれが、青春ポルノのを地で行き、コンクールでの感動という偽善を中心に、一部スター作曲家(日本の吹奏楽の世界でだけスターで、実際には時代遅れの落ちこぼれがほとんど)を神格化し、また一部強力な指導者の権力の掌握によって腐敗していくだけの完全に閉じた世界に成り下がった原因だと考えている。これは正当な音楽文化とは言えず、上記3社等が行った機会剥奪と文化蹂躙は、他に類を見ないほどの悪辣ぶりであると断じざるを得ない。
一方で、ちゃんと書かれていると感じる曲ももちろんあるのだ。そこで今回は邦人作限定で私が好きな吹奏楽作品をあえて紹介してみようと思う。良し悪し、好き嫌いは所詮主観で、音楽に正解など無いのだから、本来どうでもいいが、作曲家もファイティングポーズをとれないどころか、権威迎合と虎の威で全く戦おうという姿勢のない状態、そしてそれらを神と崇めてしまう構造の歪さは、あえて誤りであると指摘し、もっと広く大きな世界を若者に知ってもらいたいとの願いを込めて、コンクールたけなわのこの時期にこの記事を捧げたい。
さてこの手の記事を書こうとすると、どうしても古き良き作品ばかりになってしまう。それは今の「吹奏楽作曲家」諸君があまりにも情けなく、拙い知識と筆で書くから必然的にいい曲が生まれにくくなっているからに違いないが、まあそこをあえて新しい方の作品にも目を向けて語ってみようかなと思っている。
その理由は若者が多く触れる分野で昔語りばかりでは、到底理解は得られないだろうということと、芸術だと思っていたものが歌謡曲以下の価値しか無い世界から、一気に芸術作品に触れても理解が追いつかないだろうから、段階を経て行きたいという理由があるからだ。
なにはともあれ、軽めのピースから結構良いじゃんと思ったものを。
メルヘン/酒井格

写真引用:大阪音楽大学Web
酒井格は1970年大阪市出身。自身が吹奏楽経験者であり、代表作「たなばた」は高校在学中に書かれた。その後大阪音楽大学に進み、田中邦彦、千原英喜に作曲を師事、現在も吹奏楽を中心に活動している人気作曲家である。
2024年度吹奏楽コンクール課題曲IIIの当曲。私がこれを選ぶのはだいぶんと意外な気がするかもしれない。しかし酒井氏はもともと無町的な響きには抵抗があり、一貫してどの編成でも調性音楽、それもかなりロマンティックなものを書き続けた人であることを考えてみよう。どうしても初期の名作「たなばた」ばかりになり、それを超えられていないなどと言われがちだが、この曲は課題曲として重要な点、もともとたなばたの頃にあった吹奏楽を好きでたまらないという氏の目線が復活したような作品だと思えはしないだろうか。そして吹奏楽に関わり続けてきた作曲家としての経験は、課題曲という制限の強い中でこそちゃんと生きてくる。難易度設定、審査ポイントの明瞭さ、そして共感しやすく理解しやすい音楽に、ちょっとだけひねった和声がにくいではないか。昔からメルヘン好きと公言する作者の創作の哲学がそのまま表題となったことで、ものの見事に酒井格ワールドとなっている。勢い、芸術と呼ぶにはやはり圧倒的に軽い。しかし課題曲としたらこれほどにぴったりな曲も少ない。なによりもこれですぐ酒井作品とわかる作風があるのが良い。
若手「吹奏楽作曲家」はどの人も作風形成が弱く、はっきり言って誰の作品を聴いても同じ味がする。そんなものは音楽ではないし、単なるジャンクフードの量産である。しかし酒井氏の作品はその点、ちゃんと手作りのお弁当の味がする。家庭の匂いがする。そんなアットホームさを真似た量産品とはやはりどこかが違うのである。

写真引用:本人公式Web
木下牧子は我が国を代表する作曲家の一人、とりわけ合唱の世界ではスーパーレジェンドと言っても良い大きな仕事を数々成功させている。
1956年東京都生まれで、都立芸術高等学校から東京芸術大学へ進み、作曲を石桁眞禮生、黛敏郎、浦田健次郎、丸田昭三に師事した。師のひとり浦田健次郎も吹奏楽作品を残しているが、木下もまた合唱にとどまらず、吹奏楽、オーケストラ作品とジャンルを問わず活躍している。
和声感には独特のものがあり、特に四度圏に拡大していくS進行を巧みに織り交ぜ、無調ではなく拡大された調性の枠内で極めて独自の響きを導き出すことに成功している。吹奏楽作品では課題曲ともなった「序奏とアレグロ」「パルセイション」をはじめ、こちらも見事に自身の作風を表現しきっている。
シンフォニアはまだ木下の若い頃の作品であり、1988年に書かれている。もともと合唱ではなくオケ作家と自負するほどの器楽作家であったが、方舟のヒットで一気に合唱階のスターとなってしまったのは、一方で木下のある一面だけを強調する形となってしまったのかもしれない。
この吹奏楽作品は、木下の吹奏楽作品の中では近年演奏は少なくなっている。しかしハーモニービルダーとして一線を画すそのテクニックが遺憾なく発揮された名作だと言えるだろう。特に吹奏楽でしか味わえないSAXを中心とした木管ハーモニーに動的なフレーズを乗せる展開は味わい深い。
このように巨匠の作品ではその作風がちゃんと貫き通されたうえで、その編成の良さを引き出そうとする手腕が見て取れるのだ。これはいわゆる「吹奏楽作曲家」や「吹奏楽作曲家になってしまったゲーム音楽作曲家」のような存在では味わえない醍醐味と言える。その編成に合わせた楽曲、そして自身の作風という部分を両立しながら、またこの曲もそうだが、基本技術、例えば対位法の見事さなどもまたレベルが違う。そのうえでこの曲もまた多くの人に受け入れやすい顔をしている。だからこそ、もう一歩世界を広げるには最適な楽曲なのではないかと思う。ちょっとだけ背伸びしてみたら、そこには芸術の入口がちゃんと用意されているのだ。無論絶対音楽を演奏するからには、指揮者や指導者はその哲学を理解してないといけないのは言うまでもない。
―君に、できるかな?

写真引用:日本現代音楽協会
天野正道は言わずとしれた吹奏楽界のヒーローである。としてしまうのはあまりにおかしい。天野正道は劇伴においても歌謡曲においてもその足跡を残しており、吹奏楽作曲家の枠組みで語ろうとすること自体が誤りである。
1957年秋田県出身、国立音楽大学に進んで首席で卒業した。またいち早くコンピューターミュージックを学び、コンテンポラリーアートからPopsまで幅広く活動を展開している。
天野は吹奏楽では芸術性を追わない旨の発言をしている他、在学中を知る人によれば、昔から器用で作風を固定しないのが作風というところがあったというほどにその多様性は群を抜いていたという。作風は明らかにクロスオーヴァーを中心とした折衷主義であり、Popsの語法と民族音楽、伝統音楽、現代音楽の技術を自在に取り混ぜ、しなやかで柔らかい音を特徴としている。
この長い漢字のタイトルは日本の伝統的な奇書と言ってもいい「吾妻鏡」を題材に邦楽の伝統的なサウンドと、現代的な作曲法に、Popsまでまぜこんだ天野らしい作品である。昨今の吹奏楽界には曲の内容をほぼクソ長いサブタイトルで説明しきってしまっている味気ないものが多いが、その走りとなってしまった感があるのは慚愧に堪えないところだが、天野のそれはしかしあまり曲の内容に関係しないことが多い点で他と異なる。言ってみれば思わせぶりなタイトルでも、案外親しみやすかったり、その逆だったりとこの辺も一筋縄ではいかない。日本の古典に取材するという姿勢も、難しくなく理解しやすく噛み砕かれており、演奏者はやった気になるという意味で天野の音楽は特別な性格を持っているように思う。
実際に若い頃の吉原すみれと電子音でコラボした動画などをみると、その先鋭的な前衛語法は本物であり、ちゃんと書けるのだが、あえて目線を演奏する人々に合わせに行って書いているという姿勢が感じられるのも、教育的な目線としては特筆すべきことだろう。配慮というか慈愛に満ちた眼差しという点を他の有象無象に真似してほしかったところだが、どうにもその折衷法やパフォーマンス性にばかり目が奪われて、天野の骨組みを理解していない作曲家が大量に生まれてしまったのはもっとも残念なことである。
一方演奏する側には現代的表現の入口をしっかり提示しており、普及の意味でも一役買っている。そういう意味では「現代音楽意味わからん」とざっくりと切り取った動画がうるさがたに叩かれた最近の炎上をみると、天野の音楽の本質と何が違うのかうるさがたがどう語るのかその「申開き」を私はぜひ聞いてみたい。
天野の吹奏楽における活動のおかげで、音楽の入口はたしかに下がったし、吹奏楽の人気も上がった。しかしそれには本質を理解しない有象無象の出現というありがたくない副産物を生んだことについて、今後の天野自身の態度を注視していきたいものだ。
吹奏楽のための詩曲「永訣の詩」/名取吾郎

写真引用:グループ「蒼」Facebookページ
名取吾郎は1921年生まれ、戦争経験を経て池内友次郎、小船幸次郎に作曲を師事した作曲家である。陸軍軍楽隊の出身でいささか古い世代の作曲家であるが、その語法は今の軟弱な音楽に喝をいれる実に力強いものだ。基本的には12音列を中心とした作曲法を採用しており、吹奏楽作品も多く書いた。それ以外にも合唱やピアノ曲と幅広い創作分野で作品を発表しているが、その作風はいつも重く、厳しく、そして深刻さを持っている。1992年にその生涯を閉じたが、最近めっきり名前を見なくなってしまったのは残念でしか無い。
どの吹奏楽作品も傑作と言えるので選ぶのは難しかったが、やはり私はこの「永訣の詩」がもっとも名取の仕事らしい作品だと言えると思う。
永訣とは永遠の別れであり、それはまさに名取の戦争体験から来るものだろう。非常に重々しく、また覚悟に満ちた音楽であり、適当に記号化された「HIROSHIMA」だとか「FUKUSHIMA」だとかそういた表題の作品を吹き飛ばす力強さがある。この作品は我が国の吹奏楽史を超えて、音楽史上の傑作として語られるべきであり、大木正夫の音楽にも一脈通ずるところがあると思う。
天野の音楽を通じて、不協和音や複雑なリズムの面白さ、美しさに気がついた諸君は、是非こういう曲を深く深く掘り下げ、我々日本人が真に日本人たる何かを掴みとり、曲にぶつけてみてほしいと思う。そう音楽とは闘いの語句でもあるのだ。
ライフ・ヴァリエーションズ~生命と愛の歌/鈴木英史

写真引用:御本人X
鈴木英史は1965年東京都に生まれた。東京藝術大学に進み、作曲は間宮芳生、遠藤雅夫に師事している。また意外なことに尺八の演奏にも通じている。
現代作曲家としてのキャリアを積み上げて行き、間宮芳生、吉川和夫、藤家溪子、寺嶋陸也などと「MUHELY」を結成し活動したことからも、そのキャリアが非常にアカデミックで先進的なものであることがわかる。
吹奏楽作品を多く書いており、この世界ではレジェンドの一人として知られているが、いささか吹奏楽の世界に浸りすぎてしまったきらいがあるのは彼にとって良かったことなのかどうか考えてしまう。普及用の商業的な作品も多いが、そのキャリアが示す通り、実際の作曲の技術は高く大きな曲でその力を垣間見ることができる。願わくばその力でいまの風潮への迎合を辞めて、本来の鈴木イズムをもっと聴かせてほしい。
そんな鈴木の作品から一つ選ぶなら間違いなくこの曲だ。愛を堂々とテーマにしており、その中には生と死をともに織り込んでいる点で、三善晃的な円環思想的世界に、法悦を加えて愛こそがすべてを繋ぐ最も尊いものと打ち出してくるようである。
この曲の二楽章には「法悦の詩」とサブタトルがつけられ、これはもちろんスクリャービンの交響曲の表題の引用であるのは間違いない。法悦とは良い訳語だが、いわゆる愛の絶頂、エクスタシーのことであり、これを真ん中に据えている点、また第1楽章に「誕生と死」とサブタイトルを付け、これらが本質的に同義であることを印象付けている。誰かの死は誰かの生なのであるというメッセージに、愛の絶頂、そして最終楽章は堂々と「愛の歌」と題している。こういった音楽の捉え方は、先ほど経歴紹介で触れたように、左派的な思想から来る平和主義の影を強く感じる。そしてその平和をなすものは人類のお互いを愛する力だと行っているのかもしれない。先鋭的な方法ではなく、じっくりとロマンティックに聴かせる語法でこの人類永遠のテーマに真っ向挑んだ姿勢は、作曲家として尊敬できるものであるし、そんじょそこらの筆では挑めない題材だったと言えるだろう。聴き応えの面ではもう少し長くてもよいが、こんな大きなテーマをアマチュアでもちゃんと演奏できる形にまとめ上げた功績は素直に評価しなければいけないのではないだろうか。しかし人員不足の現代にあって、なかなか演奏されていないのはあまりに惜しい。
トーンプレロマス55/黛敏郎

写真引用:Wikipedia
黛敏郎は我が国を代表する大作曲家である。1929年に神奈川県に生まれ東京藝術大学の前身である東京音楽学校に入学、橋本國彦、池内友次郎、伊福部昭に師事した。また大学在学中にはJazzバンドのピアニストとしても活動をしたことが、彼の経歴のすべてを決めたとも言える。ことに伊福部昭や早坂文雄の音楽の影響を語り、その原初の光のような音楽への感動を口にする一方、NHKのスタジオでいち早く電子音に取り組み、スペクトル楽派のさきがけのような方法で傑作「涅槃交響曲」を書き上げた。
早くにフランスに留学し、トニー・オーバンに学ぶが、対立して中退、すぐに帰国した。意外なことに若い頃は左派の論客として音楽も先鋭性を持っていたが、その後日本会議の創設に携わり、極右の姿勢から政治活動を展開したことで楽壇から距離を置かれ、晩年は作曲活動が減っていた。
極めて多彩な音楽様式を使いこなし、それらを独自の視点で折衷させた音楽、全く新しいアイディアと新鮮さを讃え、常に衝撃的な作品を書いていただけに、晩年の円熟の作品が多くないのは残念の極みである。数々の名作を残し、我が国の音楽史に名を刻み1997年に絶筆となった「パッサカリア」を書きかけでこの世を去った。
こんな大作曲家だが、実は吹奏楽曲の傑作を残したことでも知られる。この曲はまだ黛の若い頃に書かれた作品で、タイトルが示すように1955年に書かれた作品である。いまの若い人にこそ聴いてほしい凄まじい楽曲だ。タイトルの示す通り力強さを持っているが、その音楽にはミュージカル・ソー、サイレンなど極めて特殊な楽器が用いられている他、日本伝統音楽のイディオムと、なんとマンボの引用まで現れる。
黛の折衷主義はこの他、「饗宴(バッカナール)」でもはっきりと見られるが、この曲もエドガー・ヴァレーズの影響や、自身のJazz経験をそのまま直截に混ぜ合わせるも、全くただのごちゃまぜにならない凄まじい筆致でまとめ上げられているのだ。
こういったある種の狂気性を持った曲は昨今少ないし、この曲はその特殊な楽器の利用から再演のハードルが極めて高くなってしまっていることは否めないが、我が国屈指の吹奏楽の名作としてちゃんと語り継がねばならないのではないだろうか。
こういった曲を気持ち悪いとか、わかりにくいとか言ってしまいがちな風潮こそ唾棄されるべきことで、本来はこういった曲こそ受け継がねばならないのだ。今の吹奏楽作曲家にこんな野心はあるのか、いや全く無いだろう。
と、今日はここまであまりにも好きな曲が多くとっても語り尽くせないので、また書く気になったら続編を書こうと思う。もちろんありがたくない皮肉とともに。