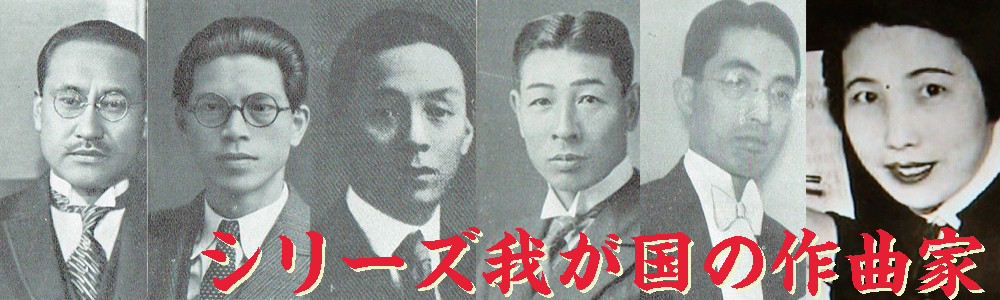
久しぶりのこのシリーズだが、今回はこのシリーズで取り上げるような忘れられてしまった作曲家でもなければ、無名のままひっそりと消えた作曲家でもない。
確固たる仕事と、足跡を残し日本音楽史にその名を刻んだ作曲家2名である。
無論一般的な知名度という観点から見たら、そこらへんのクソアイドルにも及ばないのかもしれないが、日本音楽史の中でも孤高の存在であり、自らの音楽を徹底的に追求した真の芸術家なのである。
・八村義夫という作曲家
一人目に紹介するのは八村義夫という作曲家だ。

八村義夫は1938年10月10日に東京に生まれた。
ご多分に漏れず英才教育を受けていたようで、桐朋学園大学が開いている「子供のための音楽教室」(通称「音教」)に入って勉強を開始している。
前衛の風が吹き始めていた当時、音教でも当時の最新鋭を行く作曲家が教えており、柴田南雄や入野義朗に出会ったのもこの頃だという。
しかし作曲ということになると、松本民之助に長くついて学んでおり、その後島岡譲についていることを考えると、名伯楽を渡ってきたなという印象もある。
芸大卒業後、一旦は教職の道へ進むが、大学院に再入学更に研鑽を深めたという。
しかし作品はというと、彼は生涯を通じて極めて寡作であったことが知られている。
その理由の一つは、圧倒的な個人主義による音楽への美学を持っており、徹底的に自作に厳しい姿勢を貫き、中途半端なものを書かず、また納得行かなければ破棄してしまう上に、恐ろしく遅筆であったからだ。
もう一つは、精神性の脆さというか、もともと人格形成における歪みのようなものがあったと思わせる、非常に危うい面を持ち合わせていたことによるものと思われる。

そんな中「星辰譜」という作品を完成させ、これが彼の出世作となって、桐朋学園大学、芸大と両母校で教鞭をとることとなってゆく。
お弟子さんも野川晴義、藤家溪子、久木山直、杉山洋一など特徴的な作風をもつ人々が多くなっているのもまた、八村義夫という人物を表しているように思う。
八村の音楽は一般的に超現実主義と個人語法の極端な集積として語られる面が多く、初期作品を除くとその音楽はポスト・モダン初期のネオ・ロマンのような趣があり、個人の美学を極限まで追求し、そこに論理性やある意味ではエリクチュールを遠ざけ、たった一人で心中の不安定と孤独に向き合い、それをカミソリで切りつけながら描いた絵画のような痛みの音楽である。

そんな八村の音楽が最もはっきりと形になって現れたのが、彼の代表作である「錯乱の論理」だろう。
この曲はピアノ協奏曲のスタイルをとっており、本来これを超える大作となるはずだった未完の遺作「ラ・フォリア」を除けば、唯一八村が完成させたオーケストラ曲であることも重要である。
極限まで積み上げられた彼の美意識というものは、一般のそれを遥かに凌駕しており、きっとぱっと聴いただけでは轟音との区別はつかないかもしれない。
しかしこれが彼のロマンであることは言うまでもない。


彼は「歌いたい歌もなければ、響かせたい和音もない」ということを言っている。
そんな音楽を書く基本と思われる前提が「存在しない」のになぜ音楽を書くのだろうか。
そして八村は、殺人を犯したことで罪の意識から病み、その鬱々たる精神を描き出したともいわれるカルロ・ジェズアルドの音楽を愛し、またセクシャルで極めて表現的、センセーショナルで常に破滅的な芸術を得意とするシルヴァーノ・ブソッティに心酔したのはなぜだろうか。

私はその答えの一端を彼書いた子供のためのピアノ作品である「彼岸花の幻想」に感じられるように思う。
Yoshio Hachimura: Medaitation "Higan-Bana" for piano Op.6 / Rikuya Terashima[pf]
「少年の頃に感じた言いしれぬ不安感を表現した」というこの曲は、子供のための音楽という前提を(技術難度的には)完全に無視し、自身の音楽感とそして、脆すぎる精神性をあえて打ち出して書いてきた。
そのことは彼の「生への苦しみ」の独白であろうし、それが少年時代から彼に宿っていたという告白であるように感じる。
こうして極めて不安定な土台の上に、極めて苛烈な美学を併せ持った八村が正気を保つのは難しく、彼は次第に酒に溺れてゆくこととなる。
混声合唱のための「愛の園」(アウトサイダーNo.1)やエリキサなどの充実の作品を発表するが、その頻度は芳しく無く、
相変わらず一曲の完成度の高さに比して、作品数は伸び悩んでいき、身体に不調きたし始めると一層それは顕著になった。
そしてそんな中、彼に期限なしの作曲依頼として、オーケストラ作品の依頼が来た。
その頃はすでに八村の体はぼろぼろであり、結腸がんに侵され創作ペースは絶望的な状況となっていた。
しかし本人はこの依頼に奮起し、体調を顧みない巨大な構想を用意し、作曲に取り掛かったものの、遅々として進まず完成に至る前、1985年6月15日にその命が尽きてしまったのである。

その曲は「ラ・フォリア」というオーケストラ曲であり、未完のまま演奏された音源があるのでぜひ聴いていただきたい。
この曲の解説に三善晃が寄せた文の末尾にこんな言葉があった。
「『変わりたい』と言っていた八村さんの変容のきざしが私たちにも聴こえてくるだろうか。そして猶かつ、変り得ないはずの類まれな資質もまた。」
日本音楽史においてここまで自分の闇と対峙した作曲家はいなかっただろう。
そして寡作ながらそれを発表する姿は、耳を切り落とし、鼻を削ぎ、最後には心臓まで差し出すかのような壮絶な痛みを感じる。
私は八村のようにまで自らの痛みに向かい合うこと、あるいはそれと知って逃げようともがくことはできないと強く思わされるのだ。
・甲斐説宗という作曲家
二人目に紹介するのは甲斐説宗という作曲家だ。

奇しくも八村と同じ1938年生まれ、11月15日に兵庫県に生を受けている。
変わった名前の作曲家だが、これは甲斐の生家が寺であったことに由来する。
甲斐もまた芸大に進み、長谷川良夫に師事をして卒業するが、八村とは違いここからドイツに渡って、ベルリン音楽大学でボリス・ブラッハー等に師事し、その間にはジェルジ・リゲティの教えを受ける機会もあったそうだ。
帰国後は学芸大で教鞭をとり、やはり個性的な嶋津武仁、井上郷子などを育て上げた。

甲斐の作風は一言で言えば非常に個性的な訥々とした世界観の中に、確かな狂乱が隠れていることにあるように思う。
例えば度々取り上げられる代表作の一つ「ピアノのための音楽I」はそのことが顕著に伺える作品ではないだろうか。
甲斐説宗 Sesshu Kai - Musik für Klavier; Music for Piano (1974) played by Aki Takahashi (ca.1980)
1音を執拗に聴かせる姿勢と、クラスターの殴打という素材から徐々に音楽は上方に慎重に展開してゆく。
偏執的な繰り返しを経ながらも少しずつ変容した音楽は、今度はプリペアードされたことを理由に変質してゆく。
変容と変質の先にはカオスが待ち受けており、激しい無意味の支配するコーダへ向かって霧散してゆくのだ。

この音楽に禅的な東洋思想の影響を論じることも出来るだろうし、本人の語るところの「音響作法の一種」という観点から、西洋音楽におけるポスト・モダンの潮流に位置する音楽と語ることも出来るだろう。
甲斐の音楽にはしかしそれでいながら二項対立は存在しないのである。
このことは武満徹が、ノヴェンバー・ステップスで「決して交わらない西洋と東洋の激しい対立、更には日本の伝統の中の異種対立をすべて舞台上に上げて、多層的な対立空間を見せつけたこと」と真反対のベクトルである。
真反対のベクトルと言っても、本来そこには大きな矛盾が生じてしまうものだ。それは西洋音楽が西洋音楽であるという歴史的根源と、東洋音楽が東洋音楽であるという歴史的根源を超え、それぞれの文化思想の原点までさかのぼった上での決定的な差があるからに他ならない。
しかし甲斐の音楽にはなぜかそれがない。一体なぜだろうか。
更に後年書かれた前作の続編である「ピアノのための音楽II」を聴いてみよう。
KAI Sesshu : Music For Piano II (1975-76) EMURA Natsuki, piano
甲斐の音楽性が更に淡白なものに集約され、前作で見せたようなカオティックな狂乱も鳴りを潜め、訥々とした音の中に神秘に満ちた静謐と一種の闇の美を強調させてきている。
甲斐は生前こんな事を言っている。
「盆栽にパチパチとハサミを入れる。そうやって無駄をできるだけ削ぎ落とした音楽を書きたい」

確かに甲斐の音楽を聴いたときに感じる訥々とした静謐は盆栽を鑑賞するときに感じるそれに非常に似ているようにも思う。
この背景には間違いなく、彼が寺の生まれであったことが影響していると言えるだろう。
無駄を削ぎ落としてゆく姿というのは、無に向かおうとする僧侶のサガなのかもしれないし、その静謐は寺の本堂の凛とした冬の朝の空気なのかもしれない。
それでいながら、音響作品としての立体性と、音響変移の面白さがちゃんと備わっているのは一体どういうことだろう。

その単純でいながら静謐に変化してゆく音響像には、例えばホーリーミニマリズムという形で表現されたポーランドの作曲家、ヘンリク・ミコワイ・グレツキを重ねる見方もあるようだ。
確かに日本版のまさに「ホーリーミニマリズム」とも言える甲斐の音楽の西洋性に対して、最も近似値をとった解釈であると思う。
しかし問題はそこではない。なぜ二項対立が起きなかったのかということだ。
なおポツリポツリと音を削いでいった甲斐は、その独特のイディオムを確立させるが1978年10月31日に39歳という若さで亡くなっている。
39歳にしてこの静謐の世界を作り上げてきたのかと思うと、背筋が寒くなる思いすらする。
・二人の相違点と共通点
上述のように、明らかに日本作曲史に追いて異質で奇異な孤高の作曲家である二人には、まず大きな相違点がある。
八村の音楽はあからさまにスキャンダラスな狂気が満ちていて、その果にある種のエクスタシーにも似た狂気が全面に押し出されてくることを特徴としている。
これは八村の項で書いたとおり、シルヴァーノ・ブソッティへの共感があることは言うまでもないだろう。
それに対して甲斐の音楽は静謐で、極めて禁欲的であり、そこには仏教とグレツキのようなホーリーミニマリズムとの関連が指摘されていることも前述したとおりである。
この2つの対立はあまりにも強烈なものであり、全く交わることのない二人の根本的に違う作曲姿勢と、まさに人間の差である。
そうであるはずなのに、二人の音楽には一方で強烈な共通点があるのだ。
二項対立が起きないということ。
八村の音楽はとかく個性的で、個人的な美学によって貫かれた狂気の世界である。
その音楽は西洋の一部の音楽への強い共感を得ながらも、子供の頃から変わらぬ彼自身の「不安」と強烈に結びついている。
もしかすると「不安」がもたらす「不安定」を埋めるものが「酒」であり、また狂乱と狂気であったのかもしれないし、彼にとってはそれ自身がロマンティシズムそのものだったのかもしれない。
甲斐の音楽は再三書いたとおり、西洋的なイディオムであるはずの音響作法を用いているのに、その音楽がもたらすのは日本的な無の世界感であり、諸行無常の観念である。
そこには西洋の方法論の受容と、本人の音楽観がやはり対立を起こさずに静かに同居している。
作曲を行う人は是非試してみてもらいたい。
・個人言語のみで西洋的なイディオムに対抗しうるロマンティシズムを打ち立てること
・西洋的方法論と東洋哲学をなんの違和感もなく同居させること
ほぼ無理難題であるはずのこれらのことが、それぞれの音楽で現実に起きているのだ。
なぜ二項対立が起きないのだろう。
一つの見方として、それは彼らが「真に個」であったからではないかと考えられる。
音楽は経験芸術であると、私自身は信じてやまないが、一方で個人言語の極地としても成立しうるものであるのだ。
無論それは、理論学習が面倒で堅苦しいからと逃げ出した上で批判するような、現代のバカなコンポーザーの姿とは根本的に違うことは言うまでもない。
追い詰められ、究極に探求された自己というもの、あるいは自己の不全性の直視からくる、強烈な痛みという立脚点、あるいは訥々と盆栽の枝を落としながら、ポツリと呟く独り言のような姿勢。
これら独自の「個」にたどり着いたものだけがなし得る、二項調和の世界がここにはあるのだ。
こんなことはめったに起こらない、奇跡のような状態であるが、彼らの音楽を聴くだにそのことに対する疑問は晴れ、確信に変わってゆく。
音楽とは「自分自身」でなければならないということなのである。